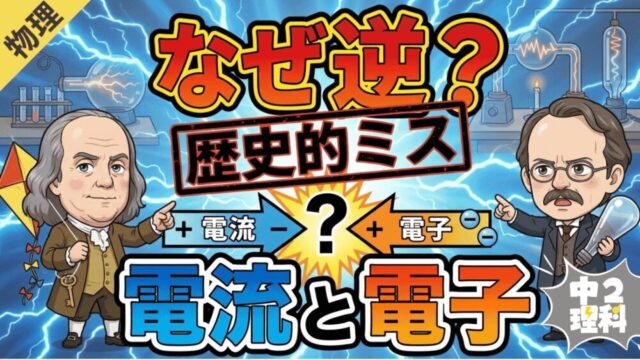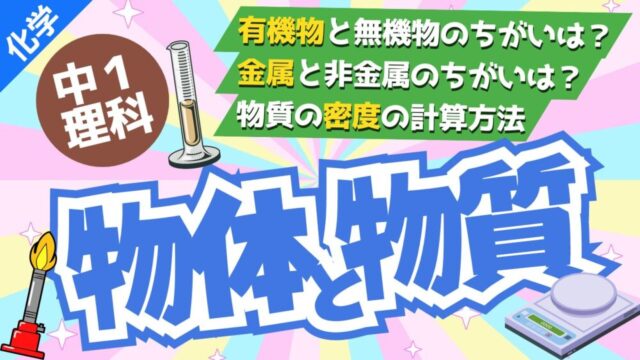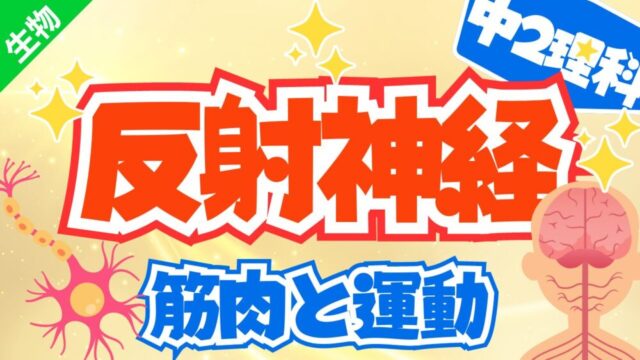この記事では、理科の化学分野が苦手な方でも理解できるよう中3理科「イオン・電離の式・中和のしくみ」をまとめて解説します。
私が17年かけて培ってきた塾講師・教員経験を凝縮しました。「授業だけじゃちょっと不安…」という人は、ぜひ最後までお読みください。
酸性・アルカリ性とイオンの基本
酸やアルカリは水にとけてイオンを生じる物質です。
この章では「酸とは何か」「アルカリとは何か」その中間である中性のしくみを、イオンの観点からやさしく整理します。
| 性質 | 酸性 | 中性 | アルカリ性 |
| リトマス紙 | 青→赤 | 変化なし | 赤→青 |
| BTB溶液 | 緑→黄 | 緑(変化なし) | 緑→青 |
| フェノールフタレイン溶液 | 無色 (変化なし) | 無色 (変化なし) | 赤色に変化 |
| pH試験紙 | 黄〜赤 (pH<7) | 緑 (pH=7) | 青 (pH>7) |
| マグネシウム | 気体が発生 (H₂) | 変化なし | 変化なし |
| 電流 | 流れる ※イオンがある | 電解質があれば流れる ※例:食塩水 | 流れる ※イオンがある |
酸とは?水素イオンのはたらき
酸とは、水にとけると電離して水素イオン H⁺を生じる物質です。
酸性の性質を示す正体は水素イオンです。
| 酸 | 電離の式 |
| 塩酸 HCl | HCl → H⁺ + Cl⁻ |
| 硝酸 HNO₃ | HNO₃ → H⁺ + NO₃⁻ |
| 硫酸 H₂SO₄ | H₂SO₄ → 2H⁺ + SO₄²⁻ |
| 酢酸 CH₃COOH | CH₃COOH → H⁺ + CH₃COO⁻ |
酸性の水溶液の特徴は次のとおりです。
- リトマス紙:青 → 赤
- BTB溶液:黄色
- フェノールフタレイン:変化なし(無色)
- pH試験紙:赤〜黄(pH1〜6)
- Mgとの反応:水素が発生
- 電流:流れる(電離してイオンを生じるため)
アルカリとは?水酸化物イオンのはたらき
アルカリとは、水にとけて電離し、水酸化物イオン OH⁻を生じる物質です。
アルカリ性の正体は水酸化物イオンです。
| アルカリ | 電離の式 |
| 水酸化ナトリウム NaOH | NaOH → Na⁺ + OH⁻ |
| 水酸化カリウム KOH | KOH → K⁺ + OH⁻ |
| 水酸化バリウム Ba(OH)₂ | Ba(OH)₂ → Ba²⁺ + 2OH⁻ |
| アンモニア水 NH₃ + H₂O | NH₃ + H₂O ⇄ NH₄⁺ + OH⁻ |
アルカリ性の水溶液の特徴は次のとおりです。
- リトマス紙:赤 → 青
- BTB溶液:青色
- フェノールフタレイン:赤色に変化
- pH試験紙:青(pH8〜14)
- Mgとの反応:変化なし
- 電流:流れる(電離してイオンを生じるため)
中性とは?イオンのつりあい
中性とは、水溶液中の水素イオン H⁺と水酸化物イオン OH⁻が等しい状態を指します。
pHは7となり、酸性・アルカリ性のどちらでもありません。
中性の水溶液として次のようなものがあります。
- 純水 H₂O
- 塩化ナトリウム水溶液 NaCl
- 硝酸カリウム水溶液 KNO₃
中性の水溶液の特徴は次のとおりです。
- リトマス紙:変化なし
- BTB溶液:緑色
- フェノールフタレイン:変化なし(無色)
- pH試験紙:緑(pH7)
- 電流:電解質がふくまれていれば流れる(例:食塩水)
よくあるQ&A(確認問題)
流れます。できた塩は塩化ナトリウム NaCl で、水にとけて電離しイオンが存在するため電流が流れます。
流れません。できた塩は硫酸バリウム BaSO₄ で、水にとけにくくイオンが存在しないため電流が流れません。
ほとんど流れません。イオンがほとんど存在しないためです。
中和とは?水と塩ができるしくみ
酸とアルカリを混ぜると中和(ちゅうわ)が起こります。
中和は、酸性・アルカリ性の性質を打ち消し合う反応です。
中和反応によって水と塩(えん)という2つの物質が生じます。
この章では、中和で何が起きているのか、イオンの視点からわかりやすく解説します。
水ができる反応
中和反応では、酸の中にある水素イオン H⁺と、アルカリの中にある水酸化物イオン OH⁻が結びついて、水 H₂O ができます。
中和で水 H₂Oが生じるしくみは次のとおりです。
- 酸は電離すると水素イオン H⁺を生じる
- アルカリは電離すると水酸化物イオン OH⁻を生じる
- 水素イオン H⁺と水酸化物イオン OH⁻が結びつき、水 H₂Oができる
中和反応は次のように表されます。
塩(えん)ができる反応
中和反応では水とともに塩(えん)が生じます。
塩とは、酸の持つ陰イオン(−)と、アルカリの持つ陽イオン(+)が結びついてできる化合物です。
よく知られている食塩もその一種ですが、中和によってできる塩(えん)は他にも存在します。
例1. 水酸化ナトリウム NaOH と 塩酸 HCl の中和
- アルカリ:水酸化ナトリウム NaOH
- アルカリの陽イオン:ナトリウムイオン Na⁺
- 酸:塩酸 HCl
- 酸の陰イオン:塩化物イオン Cl⁻
- 塩:塩化ナトリウム NaCl
- 塩の性質:無色透明、水にとける
例2. 水酸化バリウム Ba(OH)₂ と 硫酸 H₂SO₄ の中和
- アルカリ:水酸化バリウム Ba(OH)₂
- アルカリの陽イオン:バリウムイオン Ba²⁺
- 酸:硫酸 H₂SO₄
- 酸の陰イオン:硫酸イオン SO₄²⁻
- 塩:硫酸バリウム BaSO₄
- 塩の性質:白色沈殿ができる
中学理科でよく出る塩(えん)
- 塩化ナトリウム NaCl
- 硫酸バリウム BaSO₄
- 硝酸カリウム KNO₃
- 硝酸ナトリウム NaNO₃
- 硫酸ナトリウム Na₂SO₄
- 炭酸カルシウム CaCO₃
「中和=中性」ではない理由
必ずしも中和=中性とは限りません。
- 中和:H⁺ と OH⁻ が反応して水ができること
- 中性:H⁺ と OH⁻ の量がちょうど等しい状態(pH = 7)
中和反応のあとに、H⁺やOH⁻が残っていると、溶液は中性にはなりません。
| 状態 | 溶液の性質 |
| H⁺ が残る | 酸性になる |
| OH⁻ が残る | アルカリ性になる |
| 両方がぴったり反応 | 中性になる(pH = 7) |
中和は発熱反応
中和は、熱が出る反応=発熱反応です。
塩酸と水酸化ナトリウム水溶液を混ぜると、容器があたたかくなるのがわかります。
中学理科で出てくる主な発熱反応は、次のとおりです。
- 鉄の酸化(カイロ)
- 鉄と硫黄の反応(硫化鉄の生成)
- 酸とアルカリの中和
よく出る中和反応の化学反応式まとめ
本章では、テストや入試によく出る中和反応をまとめました。
【頻出】塩化水素 HCl + 水酸化ナトリウム NaOH
化学反応式:
HCl + NaOH → NaCl + H₂O
塩化水素 + 水酸化ナトリウム → 塩化ナトリウム + 水
- できる塩:塩化ナトリウム NaCl(無色透明、水にとけやすい)
- 沈殿:なし
【頻出】硫酸 H₂SO₄ + 水酸化バリウム Ba(OH)₂
化学反応式:
H₂SO₄ + Ba(OH)₂ → BaSO₄ + 2H₂O
硫酸 + 水酸化バリウム → 硫酸バリウム + 水
- できる塩:硫酸バリウム BaSO₄(白色沈殿、水にとけにくい)
- 沈殿:あり
【頻出】硝酸 HNO₃ + 水酸化カリウム KOH
化学反応式:
HNO₃ + KOH → KNO₃ + H₂O
硝酸 + 水酸化カリウム → 硝酸カリウム + 水
- できる塩:硝酸カリウム KNO₃(無色透明、水にとけやすい)
- 沈殿:なし
硝酸 HNO₃ + 水酸化ナトリウム NaOH
化学反応式:
HNO₃ + NaOH → NaNO₃ + H₂O
硝酸 + 水酸化ナトリウム → 硝酸ナトリウム + 水
- できる塩:硝酸ナトリウム NaNO₃(無色透明、水にとけやすい)
- 沈殿:なし
硫酸 H₂SO₄ + 水酸化ナトリウム NaOH
化学反応式:
H₂SO₄ + 2NaOH → Na₂SO₄ + 2H₂O
硫酸 + 水酸化ナトリウム → 硫酸ナトリウム + 水
- できる塩:硫酸ナトリウム Na₂SO₄(無色透明、水にとけやすい)
- 沈殿:なし
炭酸 H₂CO₃ + 水酸化カルシウム Ca(OH)₂
化学反応式:
H₂CO₃ + Ca(OH)₂ → CaCO₃ + 2H₂O
炭酸 + 水酸化カルシウム → 炭酸カルシウム + 水
- できる塩:炭酸カルシウム CaCO₃(白色沈殿、水にとけにくい)
- 沈殿:あり
酸性・アルカリ性の性質を調べる実験
酸性・アルカリ性の水溶液には、共通する性質があります。
この実験では、指示薬による色の変化や、金属との反応を通して、その性質をくわしく調べます。
実験の準備と手順
次の6種類の水溶液を使って、それぞれに指示薬を加えたり、マグネシウムリボンを入れたりして、性質のちがいを調べます。
使用する薬品:
- 酸性:
塩酸 HCl、硫酸 H₂SO₄、酢酸 CH₃COOH - アルカリ性:
水酸化ナトリウム水溶液 NaOH、水酸化バリウム水溶液 Ba(OH)₂、アンモニア水 NH₃ - 指示薬:
BTB溶液・フェノールフタレイン溶液・pH試験紙・マグネシウム片
- マイクロプレートに水溶液を入れる
- BTB溶液を加える
- フェノールフタレイン溶液を加える
- pH試験紙をつける
- マグネシウムリボンを入れる
各操作ごとに色の変化や気体の発生を記録し、酸性・アルカリ性の性質を確認します。
実験の結果と考察
| 水溶液 | BTB 溶液 | フェノール フタレイン溶液 | pH 試験紙 | マグネシウム |
| 塩酸・硫酸・酢酸 | 黄 | 無色(変化なし) | 黄〜赤 | 気体が出る(H₂) |
| 水酸化ナトリウム ・水酸化バリウム・アンモニア水 | 青 | 赤色になる | 青 | 変化なし |
ポイントまとめ
- 酸性:水素イオン H⁺がふくまれ、水素を発生
- アルカリ性:水酸化物イオン OH⁻をふくみ、フェノールフタレイン溶液が赤色に
- 中性:BTB溶液が緑色、pHは7
実験の化学反応式
酸の電離の式
- 塩酸 HCl → H⁺ + Cl⁻
- 硫酸 H₂SO₄ → 2H⁺ + SO₄²⁻
- 酢酸 CH₃COOH → H⁺ + CH₃COO⁻
アルカリの電離の式
- 水酸化ナトリウム NaOH → Na⁺ + OH⁻
- 水酸化バリウム Ba(OH)₂ → Ba²⁺ + 2OH⁻
- アンモニア水 NH₃ + H₂O ⇆ NH₄⁺ + OH⁻
【発展】酸とマグネシウムとの反応
Mg + 2HCl → MgCl₂ + H₂
※マグネシウム + 塩酸(塩化水素) → 塩化マグネシウム + 水素
酸性・アルカリ性の正体を調べる実験
酸性やアルカリ性の水溶液は、なぜ酸性・アルカリ性の性質を示すのでしょうか?
この実験ではイオンの動きに注目して、その正体を調べます。
pH試験紙を使った色の変化や、ろ紙を通じたイオンの移動を観察することで、水溶液の性質の根本的なしくみが見えてきます。
実験の準備と手順
使用する薬品:
- 塩酸 HCl
- 水酸化ナトリウム水溶液 NaOH
- 硝酸カリウム水溶液 KNO₃
※電流を流れやすくするために用いる - pH試験紙
実験手順:
- pH試験紙とろ紙を硝酸カリウム水溶液で湿らせる
- 湿らせたろ紙に電圧を加える
- 中央に塩酸または水酸化ナトリウム水溶液をしみこませた細いろ紙を置く
- pH試験紙の色の変化を観察する
実験の結果と考察
✅ 塩酸をしみこませた場合
- pH試験紙の赤色が、陰極(−極)側に広がっていった
→ 赤色=酸性 → 陰極=+の電気に引かれる
→ 水素イオン H⁺が移動したと考えられる
✅ 水酸化ナトリウム水溶液をしみこませた場合
- pH試験紙の青色が、陽極(+極)側に広がっていった
→ 青色=アルカリ性 → 陽極=−の電気に引かれる
→ 水酸化物イオン OH⁻が移動したと考えられる
考察まとめ
| 水溶液 | 広がった色 | 広がった方向 | 移動したイオン | 酸・アルカリの正体 |
| 塩酸 HCl | 赤色 | 陰極側(−) | H⁺ (陽イオン) | 水素イオンが酸性の正体 |
| 水酸化ナトリウム水溶液 NaOH | 青色 | 陽極側(+) | OH⁻ (陰イオン) | 水酸化物イオンがアルカリ性の正体 |
酸性の正体 → 水素イオン H⁺
アルカリ性の正体 → 水酸化物イオン OH⁻
実験の化学反応式
電離の式
- 塩酸 HCl → H⁺ + Cl⁻
- 水酸化ナトリウム水溶液 NaOH → Na⁺ + OH⁻
- 硝酸カリウム水溶液 KNO₃ → K⁺ + NO₃⁻


中和のしくみを確かめる実験①:塩酸と水酸化ナトリウム
中和反応では、酸の水素イオン H⁺ と アルカリの水酸化物イオン OH⁻ が結びつき、水ができます。
この実験では、フェノールフタレインの色の変化と塩の結晶の観察を通して、中和のしくみを目で見て確かめます。
実験の準備と手順
使用する薬品・器具:
- 塩酸 HCl
- 水酸化ナトリウム水溶液 NaOH
- フェノールフタレイン溶液
- こまごめピペット
手順:
- 水酸化ナトリウム水溶液をビーカーに入れる
- フェノールフタレイン溶液を2〜3滴加える
- 赤色が消えるまで、塩酸を少しずつ加える
- 液をスライドガラスに取り、水を蒸発させ、できた結晶を顕微鏡で観察する
理由: 液体が逆流し、ゴム球を傷める可能性があるためです。
実験の結果と考察
✅ 結果まとめ
- 水酸化ナトリウム水溶液 + フェノールフタレイン → 赤色になる
- 塩酸を加えると → 赤色が消える(無色になる)
- 液を蒸発させると → 白く四角い結晶ができた
- 容器が少しあたたかくなった
✅ 考察ポイント
- 赤色が消えたのは、中和によって OH⁻ がなくなったため
- 結晶の正体は、塩化ナトリウム NaCl
- Na⁺ と Cl⁻ が結びついてできた塩で、水にとけやすく無色透明
- 中和反応は 発熱反応 であるため、温度が上昇した
実験の化学反応式
① 中和反応の全体的な化学反応式
HCl + NaOH → NaCl + H₂O
※塩酸 + 水酸化ナトリウム水溶液 → 塩化ナトリウム + 水
② 電離の式
- HCl → H⁺ + Cl⁻
※塩化水素 → 水素イオン + 塩化物イオン - NaOH → Na⁺ + OH⁻
※水酸化ナトリウム → ナトリウムイオン + 水酸化物イオン
③ 水や塩ができる反応
- H⁺ + OH⁻ → H₂O
※水素イオン + 水酸化物イオン → 水 - Na⁺ + Cl⁻ → NaCl
※ナトリウムイオン + 塩化物イオン → 塩化ナトリウム
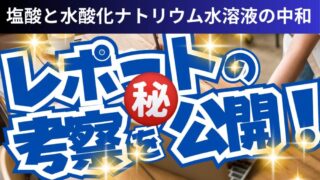
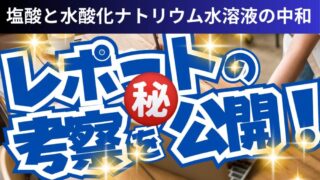
中和のしくみを確かめる実験②:硫酸と水酸化バリウム
この実験では、白い沈殿ができる中和反応を観察します。
中和によってできた塩が水にとけにくい場合、反応後に目に見える沈殿として現れます。
実験の準備と手順
使用する薬品:
- 硫酸 H₂SO₄
- 水酸化バリウム水溶液 Ba(OH)₂
手順:
- 試験管にうすい硫酸を入れる
- こまごめピペットで、うすい水酸化バリウム水溶液を数滴加える
実験の結果と考察
✅ 結果まとめ
- 白い沈殿ができた
- 容器があたたかくなった
✅ 考察ポイント
- 白い沈殿の正体は 硫酸バリウム BaSO₄
- バリウムイオン Ba²⁺ と 硫酸イオン SO₄²⁻ が結びついてできた
- 硫酸バリウムは 水にとけにくい塩 の代表例
- 中和反応で生成された塩が沈殿として現れた
- 反応後、溶液中にイオンがほとんど残らないため、電流が流れにくくなる
実験の化学反応式
① 中和反応の全体的な化学反応式
H₂SO₄ + Ba(OH)₂ → BaSO₄ + 2H₂O
※硫酸 + 水酸化バリウム水溶液 → 硫酸バリウム + 水
② 電離の式
- H₂SO₄ → 2H⁺ + SO₄²⁻
※硫酸 → 水素イオン + 硫酸イオン - Ba(OH)₂ → Ba²⁺ + 2OH⁻
※水酸化バリウム → バリウムイオン + 水酸化物イオン
③ 水や塩ができる反応
- 水ができる反応:
H⁺ + OH⁻ → H₂O
※水素イオン + 水酸化物イオン → 水 - 塩ができる反応(沈殿):
Ba²⁺ + SO₄²⁻ → BaSO₄
※バリウムイオン + 硫酸イオン → 硫酸バリウム
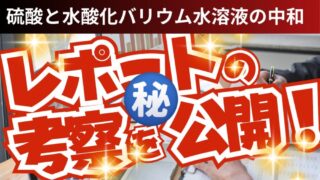
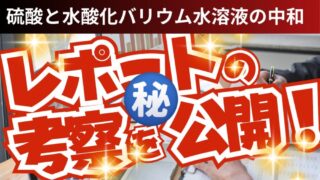
よくある質問(FAQ)|中和・酸性・アルカリ性
1. 中和=中性?
いいえ、中和しても必ず中性になるとは限りません。
- 中和:酸の水素イオン H⁺ とアルカリの水酸化物イオン OH⁻ が反応して水になること
- 中性:水溶液中の H⁺ と OH⁻ の数がちょうど等しく、pH7の状態
中和の結果、H⁺ や OH⁻ のどちらかが余ってしまうと、水溶液は中性ではなく酸性またはアルカリ性を示すことになります。
2. 塩と食塩のちがいは?
食塩は「塩(えん)」の一部にすぎません。
塩と食塩のちがい
- 「塩(えん)」とは、酸の陰イオンとアルカリの陽イオンが結びついた化合物の総称
- 食塩(しお)は、塩化ナトリウム NaCl という塩の一種
中和反応ではいろいろな塩(えん)ができます。たとえば:
- 硫酸バリウム BaSO₄ → 沈殿する白い塩
- 硝酸カリウム KNO₃ → 無色透明の塩
3. 沈殿ができる理由は?
できた塩(えん)が水にとけにくいと、沈殿が見られます。
「塩(えん)が電離しにくいため」と言い換えることもできます。
沈殿の例:
- 硫酸 H₂SO₄ + 水酸化バリウム Ba(OH)₂ → 硫酸バリウム BaSO₄(白色沈殿)+ 水
- 炭酸 H₂CO₃ + 水酸化カルシウム Ca(OH)₂ → 炭酸カルシウム CaCO₃(白色沈殿)+ 水
逆に、塩化ナトリウム NaCl や硝酸カリウム KNO₃ のように水にとけやすい塩は、沈殿せず無色透明になります。
4. ろ紙を硝酸カリウム水溶液で湿らせるのはなぜ?
ろ紙に電流をながれやすくするためです。
例:
- 硫酸 H₂SO₄ + 水酸化バリウム Ba(OH)₂ → 硫酸バリウム BaSO₄(白色沈殿)+ 水
- 炭酸 H₂CO₃ + 水酸化カルシウム Ca(OH)₂ → 炭酸カルシウム CaCO₃(白色沈殿)+ 水
逆に、塩化ナトリウム NaCl や硝酸カリウム KNO₃ のように水にとけやすい塩は、沈殿せず無色透明になります。
5. こまごめピペットの注意点は?
先端を上に向けてはいけません。
ピペットは先端を下に向け、中の液体が自然に落ちるようにして使うのが安全な使い方です。
6. マイクロプレートを使うのはなぜ?
使用する薬品や廃液の量を少なくできるからです。
マイクロプレートを用いれば、実験による環境への影響を小さくできます。
【まとめ】酸性・アルカリ性とイオンを化学反応式で理解しよう|中3理科 化学
中3化学『酸性・アルカリ性と中和、イオン』について解説しました。
中学3年の化学では「イオン」「中和」「化学反応式」はテストに出やすく、入試でも頻出です。
ただの暗記ではなく、イオンの視点でしくみを理解することが、得点アップのカギになります。
- 酸性の正体は水素イオン H⁺、
アルカリ性の正体は水酸化物イオン OH⁻ - 酸とアルカリが中和すると、水と塩(えん)ができる
- 中和でできる塩は、水にとけるもの・沈殿になるものがある
- 化学反応式・電離の式をイオンで考えるとスッキリ理解できる